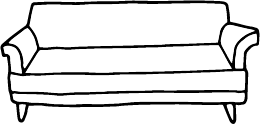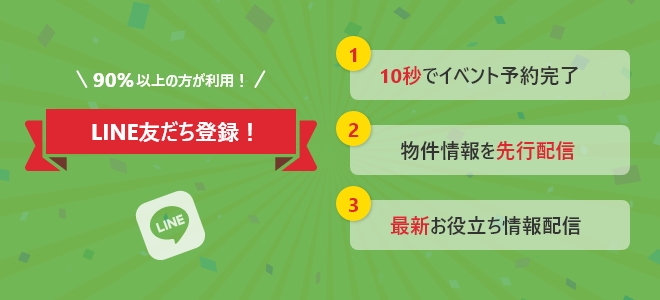江戸時代の育児書

こんにちは。DX推進室の三枝です。
私は本が好きなのですが、気になることが出てくるとそのテーマの本を何冊もまとめて読む悪癖があります。もっと満遍なく読んだ方がよいとは思いつつ、ついつい、今気になっているテーマの本ばかり買ってしまいます。
先月第一子が生まれたところということもあり、いまの関心を寄せているのは、「子育て」です。
前回のブログでは絵本について書きましたが、最近は、もっぱら育児書やエッセイを読んでいます。
どこの本屋さんも、子育てコーナーはいつも充実しています。妊娠期から思春期まで、とにかく種類が豊富で、「それだけ子育て悩みは尽きないんだなぁ」と、改めて実感しています。
人気の本を何冊か読み比べて、時代によって流行があり、子育て手法も変化しているのだと気が付きました。
そこでふと思いました。「子育て本って、いつの時代からあるんだろう?」
ざっと調べてみると、なんと江戸時代にすでにありました。
例えば、『小児必用養育草』。1714年に出版された、育児書です。内容も本格的で、新生児の抱き方や乳母の選び方、沐浴の仕方、病気の予防や教育まで、子育ての知恵が書かれています。
難しいので翻訳を頼りに、なんとなく読んでみると、当時の親たちがどんなことに悩んでいたかが伝わってきます。夜泣きや病気への不安、宮参りといった成長の節目をどう迎えるか。三百年以上の時を隔てても、親が抱える気持ちは驚くほど似ています。
読みながら、「どの時代の親も同じように悩んで、試行錯誤してきたんだな」と思うと、不思議と気持ちが軽くなりました。もちろん、どれだけ本を読んでも「完璧な答え」なんてありません。でも、そうやって悩みながら子どもを育てること自体が、人類共通の営みなんでしょう。
三百年前の江戸の親たちと同じように、「子どもの成長を願って本を手に取る」。その姿を思うと、なんだか心強く、そしてちょっとワクワクします。