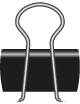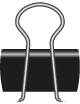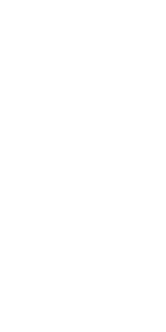2025.08.18
となりを歩く人
高校卒業後は県外でアパレルの仕事に就くことも考えていた凱也(よしや)さん。 父の設備業を継ぐ決断をしたのは、未帆さんとの出会いがきっかけだった。 「付き合ってなかったら、別の道を選んでいたかもしれません」 専務という立場になった今、上と下からの板挟みで「人生で一番辛い時期」を迎えている。 そんな日々を支えているのは、横で一緒に歩こうとする未帆さんの存在。 仕事の話をするのも、ほとんど彼女だけ。 父が一人で担っていた仕事量にはまだ届かないけれど、 6年後の正式な事業継承と、途絶えた地元の祭りの復活という夢を夫婦で共有している。 家族で夢を描く力は、小さな積み重ねから生まれる。隣を歩く人がいる限り、道は続いていく。
# MABAYUI
# セリタホームズ
# 技を受け継ぐ
# 職人
# 職人の継承
PROLOGUE
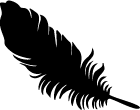
人生で最も光る瞬間は、完成の先ではなく、歩みの途中にある。 迷いながらも進み、背中を押し合いながら乗り越えていく日々。 そこに、静かで確かな光が宿る。 設備の現場から戻る車内で、 「ここ、やった現場だ」と呟く声。 父の背中を追いながら、隣には支え合う人がいる。 専務という重責を背負った今だからこそ見える景色の物語。
Chapter
1
迷いの先に
続ける理由は、そばにいた人がくれた。
春先の午後、まだ肌寒い風が町を抜けていく。
機械音が遠くで響く現場から戻ったばかりの凱也さんは、
作業着の汚れを払いながら静かに語り出した。
「最初は、この仕事をずっとやっていこうなんて思ってなかったんです」
高校を卒業後、一度は工場に勤めた。
やがて父が営む設備業の世界へ足を向けたものの、
当時は、続ける覚悟も確信もなかった。
心の片隅には、県外へ出てアパレルの仕事に就く未来も描いていた。
転機は、未帆さんとの出会いだった。
結婚を考えるようになった頃、
日々の会話の中で「この先」を具体的に思い描くようになった。
安定を求め、仕事への向き合い方も変わっていった。
「付き合ってなかったら、別の道を選んでいたかもしれません」
支え合う関係が、職業選択にまで影響を与える。
そのことを、二人は何気ない会話の中で何度も確かめ合ってきた。
一人では決められなかった道が、
二人になることで、まっすぐに見えてきた。
Chapter
2
父の歩幅
気づけば、その背中を測っていた。
高校時代、父の現場調査について行ったことがある。
昼食をはさみながら、現場と現場を移動する車内で、
父は仕事のことを多くは語らなかった。
ただ街を走りながら、
「ここ、やった現場だぞ」と何気なく教えてくれた。
「昔は父が何をしているのか、正直よくわからなかったんです」
夜遅くまで帰らなかった父。
当時の自分は、家でゲームに夢中になりながら
「遅いな」と思う程度だった。
けれど今は、その理由がわかる。
パソコンも触れないところから調べ、学び、やり遂げてきた努力を知ったからだ。
地元の人から「お父さんなら大丈夫だ」と頼りにされている姿も、
何度も目にしてきた。
その背中は、仕事の技術だけでなく、
人との信頼関係を築く重みを教えてくれる。
そして今、凱也さんは"社長の息子"ではなく、
現場と若手、そして父との間をつなぐ"専務"としての立場にいる。
二人で分担しても、父が一人で担っていた仕事量にはまだ届かない。
「今なら、父のすごさが本当にわかります」
その言葉には、尊敬と責任、そして少しのプレッシャーがにじんでいた。
やがて父の歩幅に追いつき、超えていくこと——
それが次の目標になっている。
Chapter
3
話せる場所
そばにいるから、前を向ける。
今、凱也さんは「人生で一番辛い時期かもしれない」と感じている。
後輩ができ、上と下から板挟みになる立場。
現場だけでなく事務作業も増え、責任は重くなった。
そんな日々を支えているのは、やはり隣にいる未帆さんだ。
「仕事の話をするのは、ほとんど私くらいだと思います」
産休・育休を経て職場復帰を目指す未帆さんは、
同じ会社で働く立場として、凱也さんの業務を理解しようとしている。
支えることももちろんだけど、
後ろからではなく横で一緒に歩きながら仕事ができるパートナーになりたい。
そう強く思っている。
ぶつかることは少なく、感覚は自然と近い。
だからこそ、家でも職場でも、お互いが安心できる存在でいられる。
夜、子どもたちが眠った後のリビングで、
今日あった現場の話、明日の段取り、将来のこと。
そんな会話が、凱也さんの心を軽くしてくれる。
一人で抱え込まなくていい。
その安心感が、明日への歩みを支えている。
Chapter
4
未来を紡ぐ手
子どもたちに、夢中になれる何かを残したい。
休日の午前、凱也さんは庭で子どもとボールを蹴りながら笑っていた。
その笑い声を聞きながら、未帆さんは洗濯物を干している。
二人には、地元の千曲市で途絶えてしまった祭りを復活させたいという共通の夢がある。
「自分たちが子どもの頃に感じた、あの夏のにぎわいを見せてあげたいんです」
太鼓の音、屋台の匂い、浴衣を着て歩いた夜道。
そんな記憶を、自分たちの子どもにも残してやりたい。
地域の方々と相談しながら、
夢が実現できるように一歩ずつ歩みを始めようとしている。
そんな日常の先に、もう一つ大きな節目が待っている。
6年後、父が還暦を迎えるその時に、
夫婦で会社を正式に引き継ぎたい——
地元で長年頼られてきた父の背中を継ぐことは、
凱也さんにとって誇りであり、大きな挑戦だ。
それは祭りの復活と同じように、
家族と地域に受け継ぐ"未来の約束"でもある。
「家族で夢を共有できるのは、すごく心強いです」
未来を描く力は、大きな出来事だけではなく、
こうした小さな積み重ねから生まれる。
その姿は、かつて父の背中を追った凱也さんのように、
きっと子どもたちの胸にも残っていく。

EPILOGUE
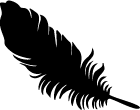
夕暮れの現場から戻る車内。
助手席の窓越しに流れる街並みの中で、
「ここ、やった現場だ」と告げる声が響く。
父から受け継いだ言葉を、
いつか自分も子どもに語る日が来るだろう。
その横顔には、
静かで確かな光が宿っていた。
隣を歩く人がいる限り、
道は続いていく。